 9/9に三条市、燕市エリアをカバーする「燕三条エフエム放送」の方々がいっぷく食堂に取材にいらっしゃいました。左側が桑原さん、右側が長谷川さんです。今回は主に長谷川さんがインタビューをされました。
9/9に三条市、燕市エリアをカバーする「燕三条エフエム放送」の方々がいっぷく食堂に取材にいらっしゃいました。左側が桑原さん、右側が長谷川さんです。今回は主に長谷川さんがインタビューをされました。
9日のいっぷく食堂のメニューは「熱々のみそゴマだれのつけ麺」です。早速長谷川さんがお客様にインタビューです。

 このお客様、実は職員のS君です。別にやらせでもなんでもないのですがたまたま美味しそうに麺をすすっていたのが長谷川さんの目に留まったのでしょう。すらすらとインタビューに答えています。いきなり話を振られたのになかなかのものです。
このお客様、実は職員のS君です。別にやらせでもなんでもないのですがたまたま美味しそうに麺をすすっていたのが長谷川さんの目に留まったのでしょう。すらすらとインタビューに答えています。いきなり話を振られたのになかなかのものです。
次に同じ席に座っていたやはり職員のO君にインタビュー。 あれ、この方、妙に緊張していますね。長谷川さんの「どちらから来られたのですか?」という質問に「さ、さ、三条です!」それはそうでしょ。
あれ、この方、妙に緊張していますね。長谷川さんの「どちらから来られたのですか?」という質問に「さ、さ、三条です!」それはそうでしょ。
そして今度はインタビュアーの長谷川さん自らつけ麺を食べながら実況レポートです。
さすがプロです。つけ麺の魅力を余すことなく、食べながらのレポート。これもある意味職人技でしょう。
 そして次にこのいっぷく食堂を管理されている小野さんのインタビューです。いやいや、語っています。物凄く語っています。
そして次にこのいっぷく食堂を管理されている小野さんのインタビューです。いやいや、語っています。物凄く語っています。
それをここで働いている遠藤君が言い放ちました。「長いよ!こういうのは3分以内で済ませなきゃダメなんだよ!」

そしていよいよこの食堂の主役でもある梅田君と遠藤君のインタビューが迫ってきました。

梅田君緊張しているのでしょうか?椅子の上でスクワットをはじめました。
なかなかこのようなインタビューは台本が無いだけ、何を聞かれるかわからないので受けるほうは難しいのですが・・・
遠藤君は? リラックスしてますね!さすが小野さ んにダメだしするだけのことはあります。いよいよ2人にインタビュー。
んにダメだしするだけのことはあります。いよいよ2人にインタビュー。
 インタビューの内容は放送を聴いていただくことにして、2人とも落ち着いた受け答えで周りをうならせました(一部周りがひっくりかえりそうになった答えもありましたが・・)
インタビューの内容は放送を聴いていただくことにして、2人とも落ち着いた受け答えで周りをうならせました(一部周りがひっくりかえりそうになった答えもありましたが・・)
無事にインタビューが終わり、ほっとしたT.Kでした。いちばんどきどきしたのはやはり小野さんのインタビューの長さでしょうか?
放送は9月13日午後三時半の街角diaryで放送されます。燕三条エフエムのお二人本当にありがとうございました。皆さんも機会があればいっぷく食堂、お立ち寄りください。
T.K











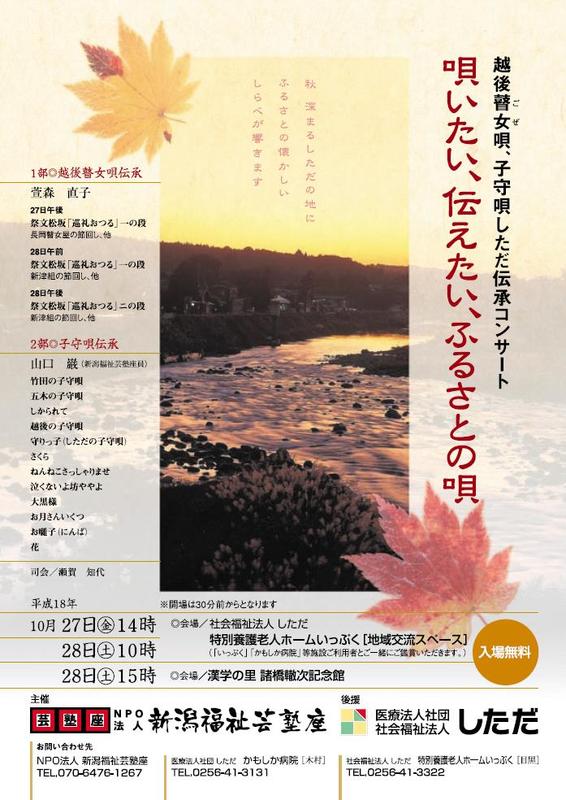
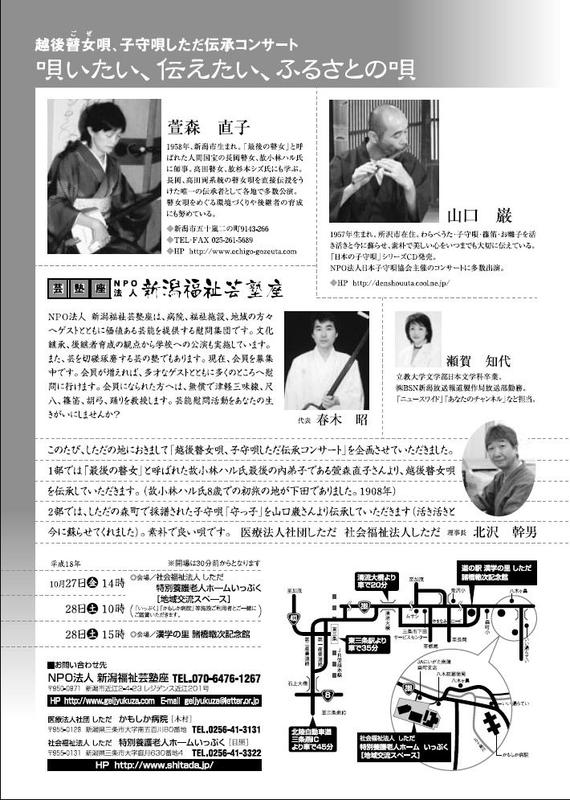
 9/18、下田の鹿峠(かとうげと読みます)地区の一部でコシヒカリの収穫が行われました。法人職員のIさんの実家は農家で、こしいぶきという品種とコシヒカリを栽培しています。今ではすっかり水が抜けた田んぼですが、水が貼っている時には、Iさんは水田で平泳ぎするのが何よりも楽しみだそうです(実話です)。 ここ何日か新潟県は雨が続き、また稲刈りは稲に朝露がつくと、稲刈り機の中でトラブルが起き易いので、通常お昼近くから行うのですが、当日は台風の影響でフェーン現象が発生し、朝から乾燥した風が吹きつけ早朝6時からの稲刈りが可能となりました。
9/18、下田の鹿峠(かとうげと読みます)地区の一部でコシヒカリの収穫が行われました。法人職員のIさんの実家は農家で、こしいぶきという品種とコシヒカリを栽培しています。今ではすっかり水が抜けた田んぼですが、水が貼っている時には、Iさんは水田で平泳ぎするのが何よりも楽しみだそうです(実話です)。 ここ何日か新潟県は雨が続き、また稲刈りは稲に朝露がつくと、稲刈り機の中でトラブルが起き易いので、通常お昼近くから行うのですが、当日は台風の影響でフェーン現象が発生し、朝から乾燥した風が吹きつけ早朝6時からの稲刈りが可能となりました。













































